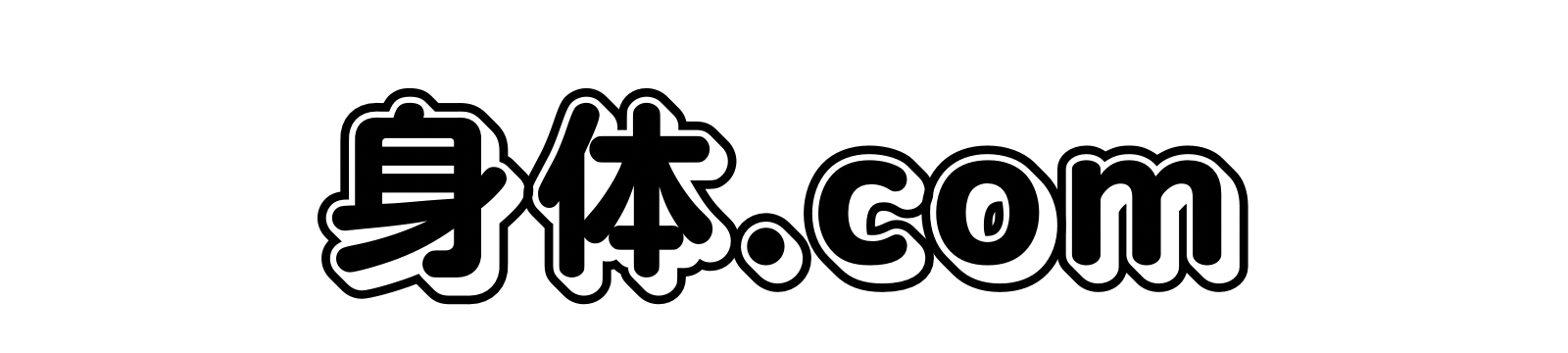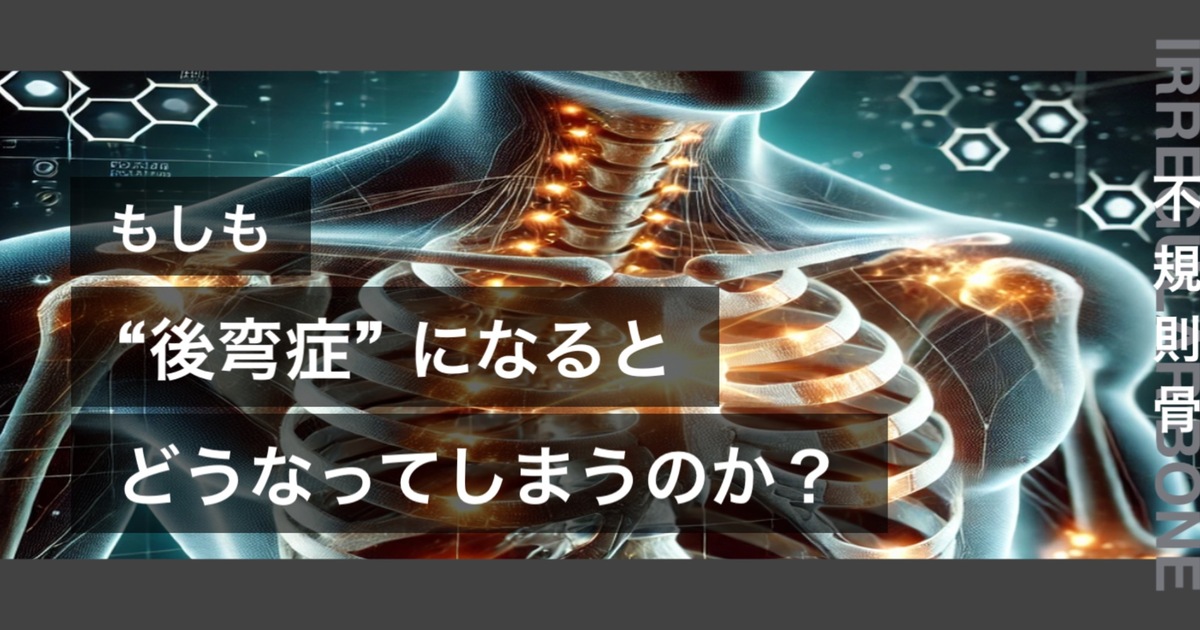どうも、担当者のヤマケンです→今回の疾病はいったいどのような病態なのでしょうか?それでは皆さん、御一緒に診ていきましょう。
:この記事は約7分で読めます
どんな病気?
後弯症(こうわんしょう)とは…脊柱(背骨)が異常に後方へ湾曲する状態を指します。通常、脊柱には生理的な後弯(胸椎の自然なカーブ)がありますが、この湾曲が過剰になると「異常後弯」となり、背中が丸くなったり、猫背が顕著になったりします。重度の場合、呼吸機能や神経に影響を及ぼすこともあります。
 ヤマケン
ヤマケンこの記事は次のような人におすすめ!
・身体の不調で当てはまりそうな病気を探している
・不規則骨疾患について勉強している
・知的好奇心が旺盛
1.原因


原因とは…病気の発症メカニズム(病因論)の中でその役割が科学的に証明されることで認識され、複数の要因が相互に影響し合って病気を引き起こす場合もあり、それは 誘因/危険因子 として区別され「その疾患を成立させるために必要で且つ十分な条件」と定義できます。
以上を踏まえると、後弯症においては多岐にわたり、主に以下のように分類されます。
|姿勢性後弯症
姿勢性後弯症
|原因
長時間の悪い姿勢(猫背/デスクワーク/スマホの使用 など)による脊柱の変形。
|特徴
若年層に多く、意識的な姿勢の改善で矯正可能。
|シェウエルマン病
シェウエルマン病
|原因
胸椎の椎体(骨)が楔形に変形する疾患で、成長期に発症する。
|特徴
痛みを伴うことがあり、姿勢の改善だけでは矯正が難しい。
|先天性後弯症
先天性後弯症
|原因
胎児期の発育異常により、脊椎の一部が正しく形成されない。
|特徴
成長とともに進行しやすく、重度の場合は外科的治療が必要。
|加齢による後弯症
加齢による後弯症
|原因
骨粗鬆症や脊椎の変性による圧迫骨折、筋力低下など。
|特徴
高齢者に多く、背中の丸まりが顕著。骨折を伴うと痛みが伴う。
|その他
その他
> 脊椎圧迫骨折
骨粗鬆症などにより、脊椎が潰れることで後弯が進行する。
> 神経/筋疾患
筋ジストロフィーや、脳性麻痺などによる筋力低下。
> 腫瘍/感染症
結核性脊椎炎(ポット病)や腫瘍による脊椎の破壊。
2.症状


症状とは…患者自身が主観的に認識する身体的または精神的な異常のことを指し、これは医療者が観察可能な徴候(しるし)と区別され⇒痛み・疲労・吐き気・不安 など、患者の自覚に基づく訴えが中心です。
症状は病気の診断や治療方針の決定において重要な情報源であり、患者と医療者のコミュニケーションを通じて初めて明らかになる点が特徴で、後弯症においては軽度から重度まで様々ですが、主な症状は以下の通りです。
|視覚的
視覚的
- 背中が丸くなり猫背が強調される
- 肩が前に出て頭部が前方に突き出る姿勢になる
|身体的
身体的
|背中/腰 の痛み
特に長時間の立位や、座位で悪化する。
|筋肉の 緊張/こわばり
特に背部や肩周辺など。
|可動域の制限
前屈や後屈が困難になる。
|重度の場合
重度の場合
|呼吸困難
肺が圧迫されるため。
|神経症状
脊髄が圧迫されると、しびれや麻痺が発生。
|内臓機能の低下
胃や腸の圧迫による消化不良など。
3.治療


治療とは…病気やケガなどの健康状態の異常を 改善/回復 させることを目的として行われる行為や介入を指し、具体的には⇒薬物療法・手術・リハビリテーション・心理的支援 などの方法が含まれ、症状の軽減/原因の除去/生活の質向上 を目指します。
治療の本質は科学的根拠に基づき、患者個々の状況に応じた最適な介入を選択することにあり、後弯症においては病因や重症度に応じて異なり、主に以下の方法があります。
|保存療法(軽度〜中等度の場合)
保存療法(軽度〜中等度の場合)
> 姿勢矯正
姿勢を意識し、正しい 座り方/立ち方 を習慣化する。
> 運動療法
背筋/腹筋 強化
体幹を支える筋力を向上させる。
ストレッチ
胸部を開く、肩甲骨周辺の可動性を向上させる。
> 装具療法(コルセット)
成長期のシェウエルマン病や、軽度の圧迫骨折に有効。
|薬物療法
薬物療法
疼痛や骨粗鬆症に対する治療法です。
> 鎮痛薬
痛みが強い場合に使用する。(NSAIDs など)
> 骨粗鬆症治療薬
骨の脆弱化を防ぐ。(ビスホスホネート製剤 など)
|手術療法(重度の場合)
手術療法(重度の場合)
> 脊椎固定術
金属プレートやスクリューを用いて、脊椎を矯正。
> 骨切り術
骨の変形が重度な場合に、脊椎の一部を除去し再建する。
手術は 神経症状が出ている場合や、日常生活に支障をきたす場合に検討されます。
4.予防


予防とは…病気が発生する前にそのリスクを減少させる、または病気の進行を抑制し健康を維持するための 行動/介入 を指し、これには⇒一次予防(発症の防止)・二次予防(早期発見と治療)・三次予防(病状の悪化防止)が含まれます。
予防は個人の行動+社会環境+医療介入 の三位一体で行われるものであり、後弯症においては以下のように日常生活の工夫が重要です。
|正しい姿勢
正しい姿勢
> 座るとき
背筋を伸ばし、椅子の背もたれを活用する。
> 立つとき
背中を真っ直ぐにし、肩を後ろに引く。
> デスクワーク
モニターの高さを適切に調整し、長時間の前かがみ姿勢を避ける。
|筋力トレーニングなど
筋力トレーニングなど
> 背筋/体幹 トレーニング
- プランク
- ブリッジ
- デッドリフト
> ストレッチ
肩甲骨周り/胸筋/腰部 を重点的におこなう。
> ヨガ/ピラティス
柔軟性を向上させる。
|生活習慣
生活習慣
> 適度な運動
ウォーキング/スイミング などを日常的に取り入れる。
> 栄養管理
特に カルシウム/ビタミンD を摂取し、骨を強化する。
> 適切な寝具
硬すぎず、柔らかすぎないマットレスを使用する。
|骨粗鬆症の予防(高齢者向け)
骨粗鬆症の予防(高齢者向け)
定期的な骨密度検査を受ける。
|転倒予防
バリアフリー環境を整えて、バランス運動を行う事。
おわりに
後弯症は、姿勢の悪化/骨・筋肉の異常 によって発症する脊柱の過度な後方湾曲です。日常的に正しい姿勢を意識し、筋力を維持することで予防が可能なので、適切な対策を実践しましょう。