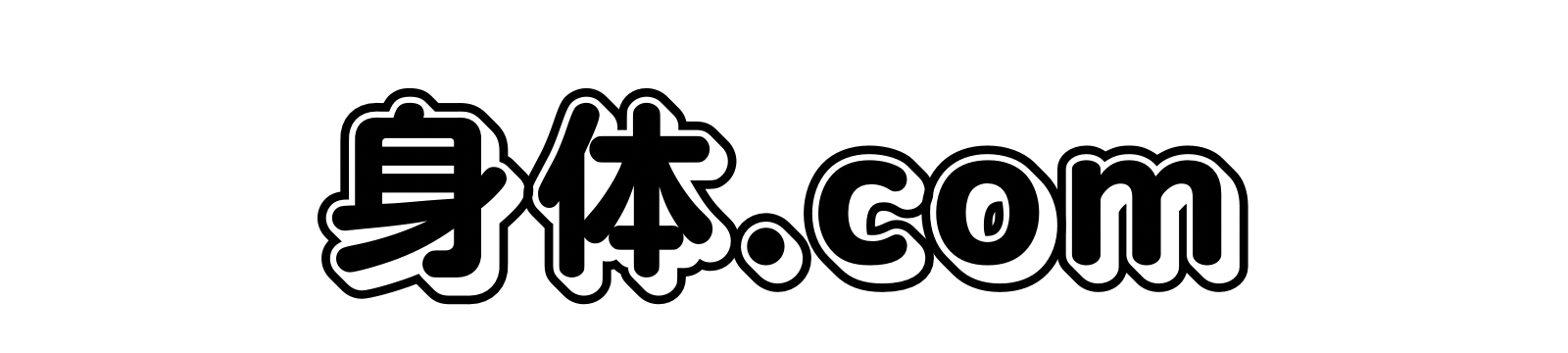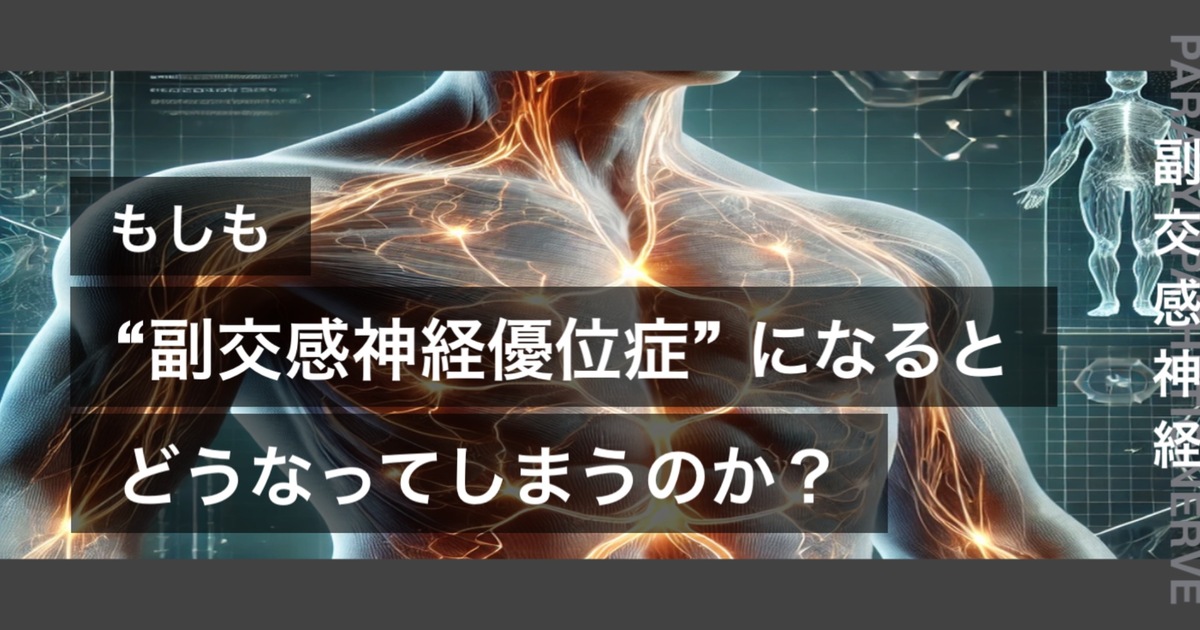どうも、担当者のヤマケンです→今回の疾病はいったいどのような病態なのでしょうか?それでは皆さん、御一緒に診ていきましょう。
:この記事は約7分で読めます
どんな病気?
副交感神経優位症(ふくこうかんしんけいゆういしょう)とは…自律神経のバランスが乱れ副交感神経が過度に優位な状態を持続することで、さまざまな身体的不調が現れる状態を指します。通常、自律神経は交感神経(活動モード)と副交感神経(リラックスモード)が適切に切り替わることで、心身のバランスを保っています。しかし、副交感神経が過剰に働くと 極端な倦怠感/低血圧/消化器系の不調 などが生じやすくなります。
 ヤマケン
ヤマケンこの記事は次のような人におすすめ!
・身体の不調で当てはまりそうな病気を探している
・副交感神経疾患について勉強している
・知的好奇心が旺盛
1.原因


原因とは…病気の発症メカニズム(病因論)の中でその役割が科学的に証明されることで認識され、複数の要因が相互に影響し合って病気を引き起こす場合もあり、それは 誘因/危険因子 として区別され「その疾患を成立させるために必要で且つ十分な条件」と定義できます。
以上を踏まえると、副交感神経が過剰に優位になる主な要因として以下のものが考えられます。
|ストレスの反動
長期間のストレス/緊張状態 の後に、身体がリラックスしようとして副交感神経が過剰に働くことがあります。
|生活習慣の乱れ
- 過度な睡眠
- 運動不足
- 不規則な食事
上記が原因で、副交感神経が過剰に優位になることがあります。
|低血圧/血流不全
低血圧体質の人/血液循環が悪い人 は、副交感神経が過剰に働きやすい傾向にあります。
|食生活の影響
消化の良すぎる食品ばかり摂取すると、消化器がリラックスしすぎて副交感神経が優位になりすぎる事もあります。
|自律神経の異常(自律神経失調症)
自律神経全体のバランスが乱れることで交感神経が十分に機能せず、副交感神経が過剰に働く場合があります。
2.症状


症状とは…患者自身が主観的に認識する身体的または精神的な異常のことを指し、これは医療者が観察可能な徴候(しるし)と区別され⇒痛み・疲労・吐き気・不安 など、患者の自覚に基づく訴えが中心です。
症状は病気の診断や治療方針の決定において重要な情報源であり、患者と医療者のコミュニケーションを通じて初めて明らかになる点が特徴で、副交感神経が過剰に働くことにより以下のような症状が現れます。
|極端な疲労感/倦怠感
休息しても疲れが取れずに、だるい状態が続く。
|低血圧/めまい
血圧が低くなりやすく、立ちくらみ/めまい が頻繁に起こる。
|冷え性
血流が悪くなり手足の冷えを感じることが多い。
|消化器系の不調
- 胃もたれ
- 便秘
- 下痢
などの消化不良が起こりやすい。
|過度な眠気/無気力
日中でも眠気が強くなり集中力が続かない。
|脈が遅くなる (徐脈傾向)
心拍数が少なくなり動悸を感じることがある。
|気分の落ち込み/抑うつ症状
副交感神経が優位になりすぎると、意欲の低下/軽い抑うつ状態 が見られることがある。
3.治療


治療とは…病気やケガなどの健康状態の異常を 改善/回復 させることを目的として行われる行為や介入を指し、具体的には⇒薬物療法・手術・リハビリテーション・心理的支援 などの方法が含まれ、症状の軽減/原因の除去/生活の質向上 を目指します。
治療の本質は科学的根拠に基づき、患者個々の状況に応じた最適な介入を選択することにあり、副交感神経優位症においては 生活習慣の改善/薬物療法 が必要になる場合があり、以下になります。
|生活習慣の改善
生活習慣の改善
> 適度な運動を取り入れる
交感神経の働きを促進して自律神経のバランスを整える。
※ウォーキング/軽い筋トレ
> 朝日を浴びる
朝の光を浴びることで交感神経を活性化し、日中の活動性を高める。
> 食生活の見直し
体を温める食事を取り入れて血流を促す。
※生姜/唐辛子
> カフェインを適度に摂取
コーヒー/お茶 に含まれるカフェインは交感神経を刺激し、副交感神経の過剰な働きを抑える効果がある。
|ストレス管理
ストレス管理
副交感神経優位症の人は、交感神経を適度に刺激するアクティブなストレス発散法(運動/趣味)、もしくは深呼吸や瞑想などのリラックス効果を取り入れることが重要。
|温冷浴/交代浴
温冷浴/交代浴
温かいお風呂だけでなく冷水シャワーを併用すると、交感神経が刺激されてバランスが整いやすくなる。
|薬物療法
薬物療法
> 低血圧がひどい場合
血圧を適度に上げる薬を処方されることがある。
> 抑うつ症状がある場合
抗うつ薬/漢方薬(補中益気湯 など)が処方されることがある。
4.予防


予防とは…病気が発生する前にそのリスクを減少させる、または病気の進行を抑制し健康を維持するための 行動/介入 を指し、これには⇒一次予防(発症の防止)・二次予防(早期発見と治療)・三次予防(病状の悪化防止)が含まれます。
予防は個人の行動+社会環境+医療介入 の三位一体で行われるものであり、副交感神経優位症を防ぐためには以下の対策が有効です。
|規則正しい生活
規則正しい生活
- 睡眠
- 食事
- 運動
上記を一定のリズムで行うと自律神経が整いやすくなる。
|朝の活動
朝の活動
朝は交感神経が働きやすい時間帯であり、運動/外出 をすると自律神経のバランスが保たれる。
|適度な緊張感
適度な緊張感
適度なストレスや刺激(仕事/趣味/社交活動)を取り入れ、副交感神経の過剰な働きを抑える。
|適温の飲食
適温の飲食
体を冷やすと副交感神経が刺激されやすくなる為、温かい 飲み物や/食事 を心がける。
|適切な休息
適切な休息
休みすぎると副交感神経が過剰になり体がだるくなる事があるため、適度な活動が大切。
おわりに
副交感神経優位症は過剰なリラックス状態が続くことで、極端な倦怠感/低血圧/消化器系の不調 などが引き起こされる状態です。原因として慢性的な ストレスの反動/生活習慣の乱れ が関与することが多いため、運動や食生活の見直しに加え適度な刺激を取り入れることが重要です。治療には生活習慣の改善が基本となり、必要に応じて薬物療法が行われることもあります。予防のためには日中の活動を増やし、適度な交感神経の活性化を意識することが大切です。